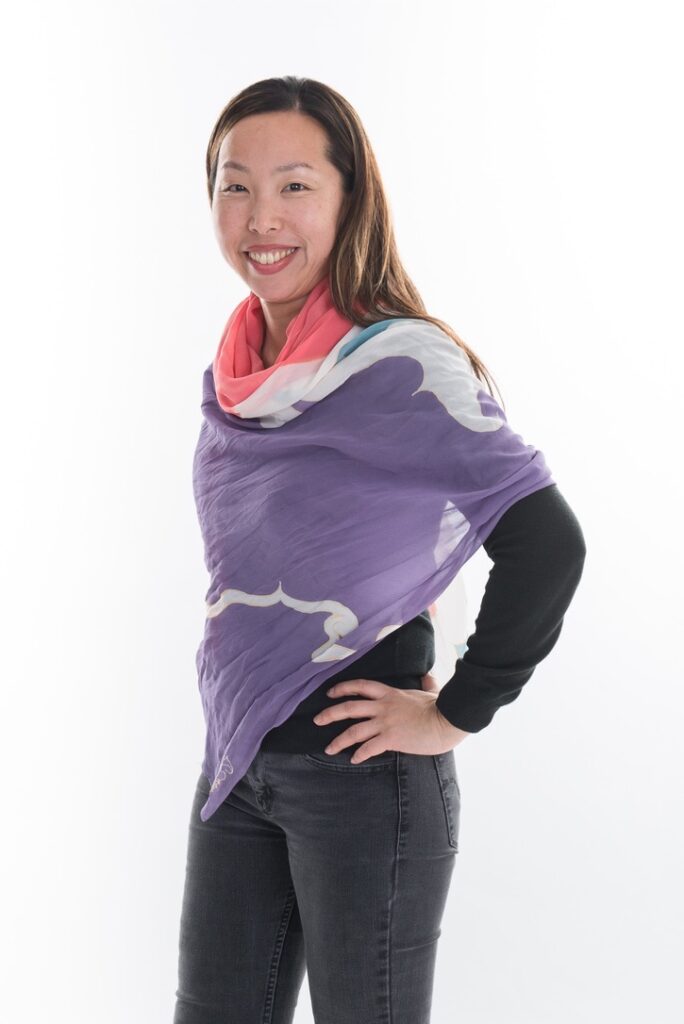メンバー紹介
鵜澤加那子博士 - 創設者
鵜澤加那子 アイヌ研究者、アーティスト、権利活動家。アイヌの文化や現代の暮らしを伝えるグローバルオンラインプラットフォーム、AinuToday.comの創設者。北海道大学先住民研究・文化多様性グローバルステーション(GSI)助教授。更に、アメリカのミシガン大学美術館のゲスト学芸員としてアイヌ美術展に関わり、ノルウェーのオスロ大学文化史博物館の研究員として、また AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoplesの編集委員としても活動している。
青年期には、アイヌに対する否定的な表象や差別に遭遇し、世間一般とアイヌの人々の見解の間に著しい違いがあることを知りました。 彼女は、21世紀にアイヌであることの意味について考えるようになりました。 それをきっかけに、アイヌの現代的な生活を表現する方法を模索するようになりました。
2008年、ノルウェーのUiT 北極大学で先住民族学の修士号、2020年に同大学でコミュニティプランニングおよび文化理解で博士号を取得しました。国際労働機関(ILO)のジュネーブオフィスで、先住民族および部族の権利に関するILO政策の促進プロジェクト(PRO 169)でインターンを経験したこともあり、アイヌ権利活動にも力を入れています。又、彼女はアーティストとして、博物館や劇場を通じて先住民族の知識の多面的な表現に貢献し、アイヌのパフォーミングアートや共同研究に取り組んでいます。

SABRA HARRIS - 寄稿者
セブラ・ハリスは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)の博士課程に在籍しています。人類学者であり民族誌学者でもある彼女は、東アジア文化研究プログラムに所属し、先住民族性と現代のアイヌのアイデンティティについて研究しています。2016年にオレゴン大学で民俗学の修士号を取得し、アニメの音楽ビデオにおけるデジタルストーリーテリングと編集について論文を書きました。
彼女が初めてアイヌに出会ったのは、テネシー州スワニーのサウス大学でアジア研究を専攻していた学部時代でした。日本の均一性の虚像について研究し始めた頃、オキ・ダブ・アイヌ・バンドに出会い、現代日本だけでなく、現代の先住民族のアイデンティティに関しても認識を鋭く問われました。 AinuToday のプラットフォームは、先住民族を過去の遺物として追いやる固定観念に疑問を投げかけるという点で重要です。 AinuToday は、アイヌ文化が遺物ではなく、博物館や歴史の中だけに存在するのではないことを示す資料を集め、整理しています。アイヌの人々は、革新的な方法で自分たちのアイデンティティを謳歌し、現代に影響を与え続けています。
セブラが鵜澤代表と初めて連絡を取ったのは サブラのUCSBでの恩師であり、鵜澤代表の友人・同僚でもあるann-elise lewallen氏を通じてでした。2021年にブリティッシュ・コロンビア大学の日本研究センターが 主催したアイヌのレジリエンスに関する鵜澤代表の講演会に参加したことがきっかけで、二人はより話し合うようになり、親しくなりました。

SCOTT HARRISON博士 - 寄稿者
スコット・ハリソン(歴史学博士)は、カナダとアジアの関係に焦点を当てた非営利団体であるカナダ・アジア太平洋財団のアジア担当シニア・プログラム・マネージャーを務めています。研究テーマは、アジア太平洋地域を中心としたグローバルな先住民族性と先住民族主義、カナダとアジアのビジネス・政策・戦略、パラディプロマシー、カナダ人のアジア関連能力の構築、日本の歴史・外交・政治、アジア冷戦史など。現在は、先住民族と冷戦に関する書籍プロジェクトおよび1970年代から1980年代にかけてのアイヌの中国訪問団に関連した2つの学会誌向け共著論文の執筆を(ゆっくり)進めています。出版物としては、「カナダの諸州とアジアにおける外交政策」 『International Journal』 (C.L.Labrecqueと共著)(2018年)、「冷戦、サンフランシスコ体制と先住民族」 『サンフランシスコ体制とその遺産』(2015年)、「オーランド諸島合意の頃の日本の先住民族アイヌ」 『北方領土、アジア太平洋地域紛争とオーランド諸島の経験』 (2009年)などがあります。 また、APFカナダのために十数本の政策記事を書いており、その多くはカナダとアジア太平洋間の先住民族の関わり合いとビジネスについて考察しています。
鵜澤加那子代表の AinuToday プラットフォームは、アイヌが主導する重要かつタイムリーな取り組みです。 過去から現在に至るまで、英語や日本語でのアイヌ関連の文献や議論の多くは、アイヌ以外の学者や専門家が独占してきました。しかし、これは変わりつつあります。 AinuToday はその一例です。鵜澤代表の先駆的な取り組みにより、 AinuToday はアイヌの学術的・芸術的作品を紹介する重要なプラットフォームとなるでしょう。 AinuToday は、単なる学術的な考察ではなく、アイヌの人々にとって重要な問題に具体的な影響を与えるような取り組みにおいて、アイヌの人々と提携する大きな可能性を提供します。私の知る限り、これは、博物館の展示以外で、アイヌの学者や職人の作品を国際的に紹介することを目的とした日本国外でのアイヌ主導の最初の取り組みの一つである可能性があります。
私は鵜澤代表の存在や今までの彼女の業績については 何年も前から知っていましたが、 マーク・ワトソン博士が私たちを正式に紹介して下さってから、共通の関心事やアイデアについて話し合うようになりました。私は、鵜澤代表および発展を続ける AinuToday のチームと共に、理解、尊敬、包摂性、そして生涯にわたるパートナーシップに満ちた未来の推進に取り組むことを待ち望んでいます。

MICHAEL J. IOANNIDES - 寄稿者
マイケル J. イオアンニデス (オレゴン州立大学で修士号、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で修士号を取得)は、カリフォルニア大学サンタバーバラ校 人類学部の博士課程4年生です。彼は10年以上にわたり、アイヌの人々の現代政治運動を勉強しています。シカゴ大学での学士論文(2010年)では、現代のアイヌのアイデンティティについて文化的能力と真正さの観点から論じ、オレゴン州立大学の修士論文(2017年)では、沙流川総合開発事業プロジェクト(二風谷ダムと平取ダムを含む)とそのアイヌ住民への影響を調査し、批判しました。博士論文プロジェクトでマイケルはアイヌモシリで民族誌的フィールドワークを実施し、アイヌの環境回復活動家とともに働き、生活することを希望しています。これは、彼らの活動が、日本政府の「土建国家」型地域開発パラダイムや、アイヌモシリで進行中の入植者による植民地主義的収奪にどのように挑戦を投げかけるかについて学ぶことを目的としています。彼は、コミュニティのニーズや要望に敏感な非搾取・非収奪型の学問を共同で生み出す手段としての先住民族の方法論にコミットすることから来る責任と関係性の倫理観に基づいて、民族誌的な活動を行っています。
博士論文の共同指導教員であるann-elise lewallen教授の授業で鵜澤代表の著作に初めて接した後、 2021年3月にブリティッシュ・コロンビア大学の日本研究センターで鵜澤代表の発表を聞き、自己紹介したことがきっかけで彼女と知り合いました。マイケルは AinuTodayに寄稿を頼まれ、大感激しました。このエキサイティングで重要なプロジェクトは、現代のアイヌの人々にとって最も重要な問題への門戸を英語の読者のために開くものです。また、アイヌの人々自身の声を高め、増幅させることで、英語の読者が、これまであまりにも疎外され無視されてきた視点に触れることができるようにすることも目指しています。マイケルは、アイヌ民族の正義のための戦いについて学び始めた10年前に、このような資料があればよかったと思っています。彼は、このような重要なプロジェクトに貢献できることを光栄に思っています。

木村真希子博士- 寄稿者
インド北東部とミャンマーの国境地帯のナガ民族独立運動の研究をきっかけに国際的な先住民族運動について興味を持ち、1999年から市民外交センターに参加。
以後、アイヌ民族と琉球/沖縄民族の国連参加や国際人権諸条約への文書提出をサポートする。 また、アジアの先住民族ネットワーク団体であるアジア先住民族連合(AIPP)とアイヌ、琉球/沖縄民族の間をつなぐ活動にも力を入れている。 現在、市民外交センター共同代表。
鵜澤代表とは2006年、2007年の国連先住民族問題常設フォーラムに一緒に参加し、共同で文書を作成するなど協力したことをきっかけに交流が続いている。
社会学者でもあり、専門はインド北東部におけるエスニック問題全般。 先住民族の権利活動や運動も対象だが、同時に移民やムスリム排斥、市民権問題なども視野に入れる。 現在、津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科で国際社会学や先住民論を担当。
2021年、AinuToday開設時には、アイヌ権利活動の項目や日本語版への翻訳で貢献した。 2020年のウポポイ開業でアイヌ文化や言語には注目が集まるものの、その土台となる権利、特に土地や資源について日本でほとんど議論されていないことに危機感を覚えている。
AinuTodayの存在は、先住権について議論を喚起する非常に良い場所になるのではと期待している。